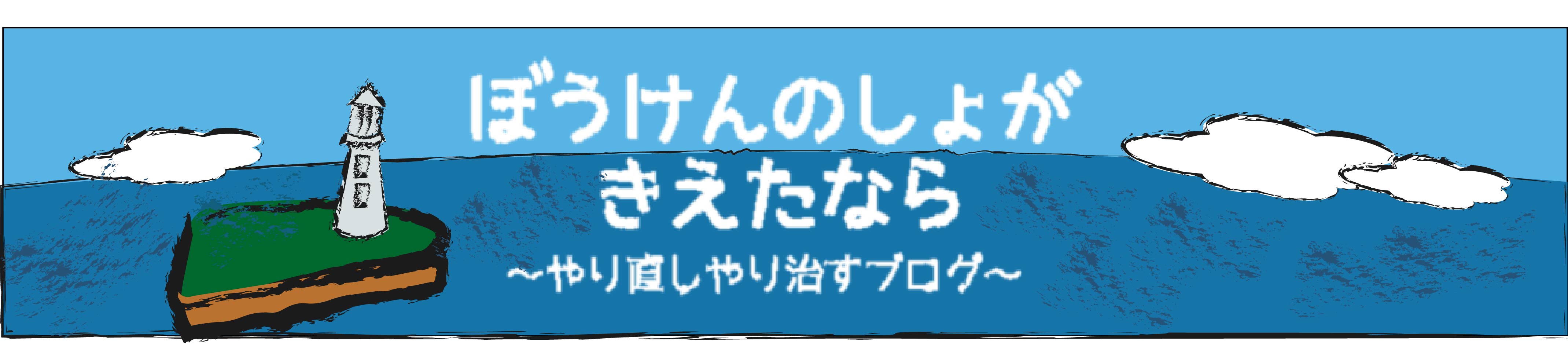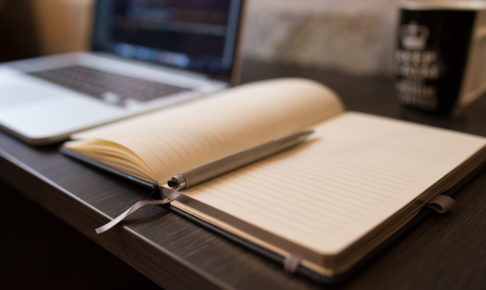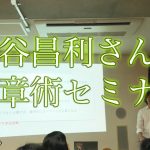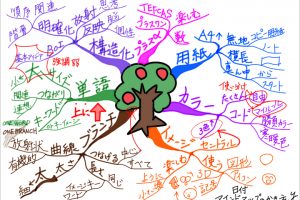こんにちは。
やまざきたかし( @yamazaki_1205 )です。
以前、「マインドマップの書き方」を習いに来た妹の“サトミ”が再びぼくのオフィスを訪ねてきました。

今度は何があったのでしょうか…?
読書の記録としてノートを作ることの意味












今回は、話の流れとして以下のように進めていきます。
- 読書の記録としてノートを作るオススメの方法(全体的な話)
- マインドマップで読書の記録をやるとしたら?
読書の記録としてノートを作るオススメの方法




ということで、「本によって強弱をつける」お話でした。
仕事でもプラベートでも、何か新しいことを学ぶ必要がある時は、「入門書を読む」ことがオススメです。
この場合、ページ数が多くない本をザッと読み、全体像を学ぶことができます。
その先のステップで基本書や専門書を読む時は、必要な部分を重点的に読むことが可能になりますが…。
もしこのステップで完璧を目指そうとすると、難解かつそれほど必要でない部分にこだわるあまり、必要な部分にたどり着けないまま挫折する可能性があります。
そもそも、「なぜこの本を読んでいるのか?」という目的を意識して、強弱をつけて読み進めてみましょう。
読書記録ノートの項目:基本情報
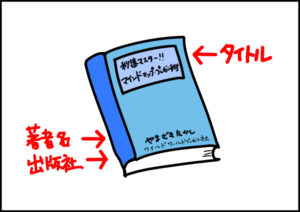


- タイトル
- 著者名
- 出版社
があるといいね。ただ、少なくともタイトルさえあれば後はいくらでも調べられるよ。

- 本の内容のうち、必要な部分・重要な部分
をまとめていく。



学生時代は特に、ノートを取る際の制約が色々とあったかもしれません。
しかし、読書記録としてのノートは「必要な部分をまとめておけばOK」という視点を常に意識しておくといいでしょう。
しつこいと言われても「完璧を目指す必要はありません!」と書いておきます。
読書記録ノートの項目:情報面・知識面
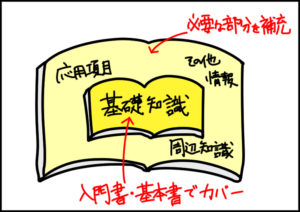






- 教科書→基本書・入門書
- 資料集→その分野における多くの本
- 問題集→「〇〇実践編」や「記入形式」部分が多い本







- 周辺知識を知って初めて本質が分かる時がある
- 図解などの表現の仕方・例え話によって理解できることがある






- 感じたこと・意見
- もっと詳しく知りたいこと
- 疑問・質問







マインドマップで読書の記録をやるとしたら?




- 目次を活用する
- 「まとめ」を活用する










- キーワードから派生したやり方






- 本文中のキーワード
- キーワードのつながり・相互の関連性
- 重要度の階層構造

さて、ここまで読書記録としてのノートについて考察してきました。
このブログの中にもカテゴリーとして「読書+マインドマップ」がありますので、参考にしてみてください。
それではまた。